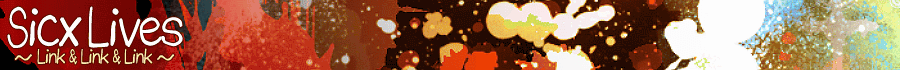
| << LIST |
[Notice] [RuleBook] [Result] [Lounge] [Link] |
| 世界共通! No.231 本 | 文箭 |
本を読むのが好き! 本を蒐集するのが好き! 本を学問的に見るのが好き! 装丁や形が好き! 本というものが、とにかく大好き! 以上に一つでも当てはまったならば、是非ご参加下さい。 当コミュニティーでは、本が好きな方を募集しております。 本のみならず、書物全般(巻物や帖のもの)、また非書物(手紙、古筆切、他)なども範囲に含みます。 条件に当てはまれば、PL、キャラクター問いません。お気軽にお越し下さい。 主張用ではありますが、たまにコミュ主が呟くこともあります。 他にも、オススメの本や書物に捧げる熱い思いなどなど、交流の場として活用して頂ければ幸いです。 |
| コミュニティメッセージ |
文箭(231)からのメッセージ: 『その人の専門や興味がどんな方角をさしていようと、ことばが表現の手段である限り、人は時を場合とに応じ、ことばの意味を辞書によってたしかめなければならない必要に迫られる。だから書物のあるところ、必ず辞書があるといってよい』 この方は辞書類を500冊以上所有しておられました。また、辞書は引くためだけでなく、読むためにもある――と。 『辞書には、政治家や説教師によく見かける偽善的なことばづかいがなく、エスマンは辞書を引くよりはむしろ読むことを楽しみとした。私はエスマンに賛成である』」
バニー&ラスティ(1132)からのメッセージ:
ミコト(1619)からのメッセージ:
わらわら〜ず(1970)からのメッセージ:
|
| コミュニティ参加者 |
 PL「緊張かぁ… 緊張してるっていう自覚はないかなぁ。むしろ気を抜きすぎじゃねえのってよく言われるんだ(…)でもまぁ、寝ていればだいたい治りますので!きっと問題ないです!」
PL「緊張かぁ… 緊張してるっていう自覚はないかなぁ。むしろ気を抜きすぎじゃねえのってよく言われるんだ(…)でもまぁ、寝ていればだいたい治りますので!きっと問題ないです!」 ミコト「紙の誕生は、何かを記すことにおいて最も難しく偉大な一段階ですね!?
ミコト「紙の誕生は、何かを記すことにおいて最も難しく偉大な一段階ですね!? いんちゃん「鳥の子? ぼくらみたい? 何で鳥の子って言うのですか?
いんちゃん「鳥の子? ぼくらみたい? 何で鳥の子って言うのですか? いんちゃん「金物に刻むから、かくかくしてる文字なのかな?」
いんちゃん「金物に刻むから、かくかくしてる文字なのかな?」