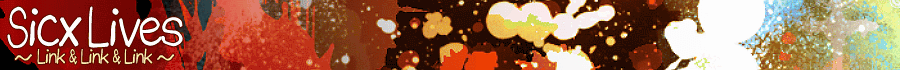
| << LIST |
[Notice] [RuleBook] [Result] [Lounge] [Link] |
| 世界共通! No.231 本 | 文箭 |
本を読むのが好き! 本を蒐集するのが好き! 本を学問的に見るのが好き! 装丁や形が好き! 本というものが、とにかく大好き! 以上に一つでも当てはまったならば、是非ご参加下さい。 当コミュニティーでは、本が好きな方を募集しております。 本のみならず、書物全般(巻物や帖のもの)、また非書物(手紙、古筆切、他)なども範囲に含みます。 条件に当てはまれば、PL、キャラクター問いません。お気軽にお越し下さい。 主張用ではありますが、たまにコミュ主が呟くこともあります。 他にも、オススメの本や書物に捧げる熱い思いなどなど、交流の場として活用して頂ければ幸いです。 |
| コミュニティメッセージ |
文箭(231)からのメッセージ:
玄深(1294)からのメッセージ:
ミコト(1619)からのメッセージ:
わらわら〜ず(1970)からのメッセージ:
|
| コミュニティ参加者 |
 玄深「緩りとお待ち申し上げておりますよ、主殿」
玄深「緩りとお待ち申し上げておりますよ、主殿」 >ミコト殿
>ミコト殿 玄深「全くその通りにございます、己の頭の中のイメージと中々合致せず…別物と思おうとはすれど、次元を超える難しさよ」
玄深「全くその通りにございます、己の頭の中のイメージと中々合致せず…別物と思おうとはすれど、次元を超える難しさよ」 玄深「源氏物語に関してはそうですねぇ、背後が中谷殿贔屓でおります故に多少の贔屓目が。
玄深「源氏物語に関してはそうですねぇ、背後が中谷殿贔屓でおります故に多少の贔屓目が。 ミコト「コミュ長、ご無理なさらずですよー、と述べつつ…」
ミコト「コミュ長、ご無理なさらずですよー、と述べつつ…」 ミコト「自作で、かつ、辞書ですとな…!
ミコト「自作で、かつ、辞書ですとな…! いんちゃん「おやすみ、おやすみ〜、休憩ですね〜♪
いんちゃん「おやすみ、おやすみ〜、休憩ですね〜♪