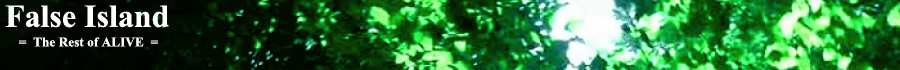レナーテ(385)からのメッセージ:
 レナーテ「……今までコミュの発言だけは続けていたと言うのに、前回はチキレに負けてしまった。 レナーテ「……今までコミュの発言だけは続けていたと言うのに、前回はチキレに負けてしまった。
何とも、口惜しい。やはり余裕を持って行動せねばならんな」
 マリア「さらりと話すと説明不足でよくわからず、詳しく話すと長すぎてよくわからず。 マリア「さらりと話すと説明不足でよくわからず、詳しく話すと長すぎてよくわからず。
もっとわかりやすく説明できれば良いのですが、まだまだ未熟なもので……。
まあ、わからない話は適当に読み飛ばしていただけると幸いです!>璃珀さん」
 レナーテ「レンズのみで5万円とは。普通のレンズとどのような差があるのか知りたいところだ。 レナーテ「レンズのみで5万円とは。普通のレンズとどのような差があるのか知りたいところだ。
もっとも、素人ではその性能差を活かすのはなかなか難しいのだろうが……>ミィ殿」
 マリア「さて、以下は前回送信する筈だったコミュメッセです。 マリア「さて、以下は前回送信する筈だったコミュメッセです。
後は貼り付けるだけだったんですけどね……」
 マリア「では、前回の続きとまいりましょう。 マリア「では、前回の続きとまいりましょう。
前回は七事式の種類について簡単に説明した所まででしたね。
今回はそれぞれについて茶道の基礎知識を交えながら説明していきます」
 マリア「まずは『茶カブキ』から。 マリア「まずは『茶カブキ』から。
これは、三種類五服の濃茶を飲んでその銘を当てると言うものです。
実は私はやった事がありません。見た事はあるのですが」
 マリア「正直、五服も濃茶を飲むのは辛いと思います。 マリア「正直、五服も濃茶を飲むのは辛いと思います。
一般的に、茶道をやってない人のイメージする『抹茶』は薄茶です。
濃茶と言うのは、簡単に言えばその二倍の量のお茶を半分のお湯で点てるものだと思って下さい。
『お茶を練る』との言い方をするくらいどろどろしています。
ちなみに、全員が一つのお茶碗で飲みます(人数によっては分けます)」
 マリア「勿論、薄茶よりも上質の部分を使ってはいるのですが……。 マリア「勿論、薄茶よりも上質の部分を使ってはいるのですが……。
あんまりがぶがぶ飲めるものではありません。
また、練り方によって味が相当に変わります。
上手い人が練れば甘みすら感じますが、慣れてない人が練れば物凄く苦いです」
 マリア「ここで豆知識。 マリア「ここで豆知識。
濃茶を練る際、二度に分けてお湯を入れるのですが……。
最初のお湯が不足すると苦くなり、お茶の塊もできやすいです。
最初はやや多めに入れた方が、飲みやすく美味しい濃茶になります。
ただ、お湯が多すぎると今度は折角のお茶の味が薄まってしまうので気をつけて下さい」
 マリア「まあ、そんな訳で茶カブキをするなら亭主は慣れた人じゃないとそもそも成立しませんよ、と。 マリア「まあ、そんな訳で茶カブキをするなら亭主は慣れた人じゃないとそもそも成立しませんよ、と。
もっとも、慣れてない人が七事式するとも思えませんが!
さて、本題に戻りましょう」
 マリア「最初に、客は三種のうち二種を飲みます。 マリア「最初に、客は三種のうち二種を飲みます。
これはいわば練習で、この時点では銘が明らかにされています。
最後の一つは銘を明らかにせず、この時点で飲む事もありません
その後、本番では三種をシャッフルして出し、客はそれぞれがどの茶であるかを当てるのです」
 マリア「その記録を執筆(しひつ)と言う人が書いて、正解者にはその記録が与えられます。 マリア「その記録を執筆(しひつ)と言う人が書いて、正解者にはその記録が与えられます。
そんな記録貰っても……と思うかもしれませんが、執筆は偉い人が務める事が多いのでそれなりに価値があります。
家元での利休忌では、家元宗匠が執筆を務められます」
 マリア「この原型となったのが前回も名前の出た『闘茶』で、茶道成立前から行われていました。 マリア「この原型となったのが前回も名前の出た『闘茶』で、茶道成立前から行われていました。
元々はお茶を数十服も飲み比べて、栂尾のお茶(本茶)かそうでないか(非茶)を当てるものだったようです。
ただ、競技性を引き継いでいるものの茶カブキの根底にはやはり禅の思想がありまして、七事式考案の際の協力者『無学宗衍』和尚は『干古干今截断舌頭可知真味』……つまり、悟って初めて真の味を知る事ができる、と言っています。
まあ、その思想を理解して茶カブキをしていた人は少なかったでしょうが……」
 マリア「何と、一つしか説明できませんでした。 マリア「何と、一つしか説明できませんでした。
脇道に逸れてばかりでしたしね……。次回からはスピード上げます」
 マリア「と、前回分はここまで。スピード上げるどころか停滞してしまいました。 マリア「と、前回分はここまで。スピード上げるどころか停滞してしまいました。
もう枠が無いですが、今回は廻り炭について簡単に話……す前に、茶道の炭点前の基礎知識を。
どうにも、何かを説明しようとするとその前提を説明する必要が出てきて長くなってしまいますね…。
このままだと七事式だけで10回くらい消費してしまいそうなので、多分途中で打ち切ります」
 マリア「茶道においては湯の具合が大変重視されます。以前もお話しましたね。 マリア「茶道においては湯の具合が大変重視されます。以前もお話しましたね。
湯の煮え加減が悪いと美味しいお茶を点てる事が出来ないからです。
その為、必然的に炭の入れ方も重要になります。ただ炭を足すだけではなかなか火力は出ません。
特に、廻り炭を行う『炉』においてはそれが顕著です。
なお、炉とは床に埋め込まれた42cm四方の囲炉裏の事。寒い時期はこれに釜をかけます。
ちなみに、暑い時期には『風炉』と言う……物凄く乱暴な言い方をすれば火鉢みたいな物を使います」
 マリア「で、何故ただ炭を詰め込んでも火力が出ないかと言いますと……。 マリア「で、何故ただ炭を詰め込んでも火力が出ないかと言いますと……。
炉の形を □ としますと、その中は ◇ ←こんな形に灰の山によって区切られています。つまり、実際に使える空間は半分程度。
そこに釜を乗せる為の五徳までありますので、かなり狭いスペースに炭を入れる事になります。
通常、火種は真ん中に置くものですから、狭いスペースに何も考えず炭を足したところで火種に空気が行かずまともに燃焼しない訳です。上部は釜で塞がれていますしね。
……時には一酸化炭素中毒になったなんて話も。稀なケースではありますが」
 マリア「きちんを火力を出せるような炭のつぎ方は、慣れないとなかなか難しいです。 マリア「きちんを火力を出せるような炭のつぎ方は、慣れないとなかなか難しいです。
廻り炭は、それを学ぶ為のものなのですが……。
ある理由により、初心者どころか熟練者も頭を悩ませる事になります。
その理由についてはまた次回に」
|