レナーテ(385)からのメッセージ:
 マリア「さて。今回は何か茶道具について話すと予告しましたが……。 マリア「さて。今回は何か茶道具について話すと予告しましたが……。
そうですね、とりあえず釜について話すとしましょうか」
 マリア「釜は茶道具のなかでもかなり重要視されていまして、茶会を催す事を『釜をかける』と言うほどです。 マリア「釜は茶道具のなかでもかなり重要視されていまして、茶会を催す事を『釜をかける』と言うほどです。
まあ、そもそも釜が無ければお湯を沸かす事が出来ないですから当たり前ではありますけど」
 マリア「少し話はそれるのですが……。 マリア「少し話はそれるのですが……。
茶道では、湯相(釜の煮え具合)にかなり気を遣います。ぬるいのは論外ですし、あまり煮えたぎっていてもいけません。茶の風味が損なわれてしまいますからね。
茶事においても濃茶の後、薄茶の為にわざわざ炭を整えるんですよ。
『お客に美味しいお茶を飲んでもらう』のが茶事の目的ですから、その為の手間は惜しまないと言う事です」
 マリア「湯相への気の遣い方は、釜の煮える音を細かく分類し一つ一つ名前を付けている事からもわかります。 マリア「湯相への気の遣い方は、釜の煮える音を細かく分類し一つ一つ名前を付けている事からもわかります。
もっとも呼び名は統一されている訳ではなくて、例えば利休は『蚯音・蟹眼・連珠・魚目・松風』としていますが、『魚眼・蟹眼・雀舌・小涛・大涛・無声』と書かれている本もありますし、調べてみたら『魚目・蚯音・岸波・遠波・松風・無音』と言う呼び方もあるそうです。
ちなみに『蚯音』はミミズの鳴き声と言う意味。
ミミズは鳴かないよ!とツッコミを入れたらきっと負けなのでしょう」
 マリア「さて、釜の話に戻りましょう。 マリア「さて、釜の話に戻りましょう。
かつて釜の三大産地と言えば天明、芦屋、京でした。その中で最も質が高いとされているのが芦屋釜です。
芦屋釜は形と文様が美しく、なおかつ非常に薄く軽かったためとても人気がありました。
しかし、庇護者であった大内氏が滅亡したため衰退。廃絶してしまいます」
 マリア「職人達は各地に散らばりましたが、芦屋時代と同等の作品が作られる事は二度とありませんでした。 マリア「職人達は各地に散らばりましたが、芦屋時代と同等の作品が作られる事は二度とありませんでした。
そして、現在に至るまで芦屋釜は再現できていません。ロストテクノロジーと化してしまったのです。
特に胴部の薄さの再現は困難で、最も薄い作品ではなんと2ミリ。
現在の技術では、3ミリ程度が限界だそうです」
 マリア「重文指定を受けている釜は九つあるのですが、そのうち八つが芦屋釜と言う事実も芦屋釜の素晴らしさの証明となるでしょう。 マリア「重文指定を受けている釜は九つあるのですが、そのうち八つが芦屋釜と言う事実も芦屋釜の素晴らしさの証明となるでしょう。
ちなみに、残り一つは天明釜です。京釜は無し。
その九つを列挙すると、以下の通りです。
芦屋浜松図真形釜 蘆屋松梅図真形釜 蘆屋浜松図真形釜 蘆屋七宝文真形釜
蘆屋無地真形釜 蘆屋霰地楓鹿図真形釜 蘆屋霰地真形釜 蘆屋楓流水鶏図真形釜 天明極楽律寺尾垂釜」
 マリア「もっとも、一般には芦屋釜より天明釜の方が良く知られていると思います。 マリア「もっとも、一般には芦屋釜より天明釜の方が良く知られていると思います。
戦国武将の松永久秀が『古天明平蜘蛛』と共に自爆したと言う逸話は有名ですからね。
『壊されていなければ国宝間違いなしだったのに』と言う意見もありますが、上記の一覧を見る限りでは現存していたとしても国宝は難しかったかなと……」
 マリア「なお、この古天明平蜘蛛ですが壊されていなかったと言う説もあります。 マリア「なお、この古天明平蜘蛛ですが壊されていなかったと言う説もあります。
現在『浜名湖舘山寺美術博物館』の目玉展示品となっている平蜘蛛釜がそれだとか何とか。
まあ本当かどうかはわかりませんが、とりあえずその釜は重文にも指定されていません」
 マリア「……あれっ、大した事も喋らないうちに枠が尽きましたね。 マリア「……あれっ、大した事も喋らないうちに枠が尽きましたね。
いえ、いつもの事ですけど。
次回は……何を話しましょうね。まだ決めていません。
あと、異動になったので今後は水道の話題は減ると思います」
ミィ&仁義(222)からのメッセージ:
 ミィ&仁義「なぁるほど。決して骨肉の争い、ということではなく。 ミィ&仁義「なぁるほど。決して骨肉の争い、ということではなく。
各々が道場開いたって感じなわけですねぃ。
良い勉強になりましたよぅ。親父さんの奮闘っぷりが凄いですけど(笑」
エリィ(229)からのメッセージ:
 エリィ「そういえば数回前に出そうと思っていた話を思い出したので出してみますね。言語によって読み方が違うという話の延長なのですが。」 エリィ「そういえば数回前に出そうと思っていた話を思い出したので出してみますね。言語によって読み方が違うという話の延長なのですが。」
 エリィ「昔お話ししたように、現状の日本の化学教育ではまだドイツ語が根強いです。そのためドイツ語読みをカタカナにして教えていることが多いのですが……。」 エリィ「昔お話ししたように、現状の日本の化学教育ではまだドイツ語が根強いです。そのためドイツ語読みをカタカナにして教えていることが多いのですが……。」
 エリィ「たとえば炭水化物の種別分けに、アルカン・アルケン・アルキンという紛らわしい物があります。それぞれ綴りはalkane・alkene・alkyneとなります。」 エリィ「たとえば炭水化物の種別分けに、アルカン・アルケン・アルキンという紛らわしい物があります。それぞれ綴りはalkane・alkene・alkyneとなります。」
 エリィ「あ、ちなみにどういう物かは面倒なので説明しません。興味のある方は調べてみてください。」 エリィ「あ、ちなみにどういう物かは面倒なので説明しません。興味のある方は調べてみてください。」
 エリィ「さて、これらを現在国際語である英語で発音するとどうなるかというと、alkaneはアルケイン、alkeneはアルキーン、alkyneはアルカインという感じになります。見事に一個ずつずれてしまうわけですね。」 エリィ「さて、これらを現在国際語である英語で発音するとどうなるかというと、alkaneはアルケイン、alkeneはアルキーン、alkyneはアルカインという感じになります。見事に一個ずつずれてしまうわけですね。」
 エリィ「おかげで、英語に慣れないうちは何が何を指しているのかわけがわからなくなるという事態が頻発しています。困ったものですが教育事情が絡んでいる以上解決が難しいのも事実のようです。こんなつまらないことで充分な国際競争力が発揮されないとなればとても情けない話ですよね……。」 エリィ「おかげで、英語に慣れないうちは何が何を指しているのかわけがわからなくなるという事態が頻発しています。困ったものですが教育事情が絡んでいる以上解決が難しいのも事実のようです。こんなつまらないことで充分な国際競争力が発揮されないとなればとても情けない話ですよね……。」
| 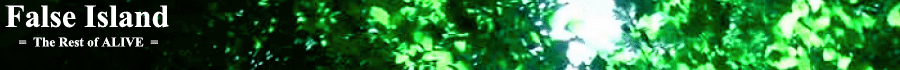

 ミィ&仁義「なぁるほど。決して骨肉の争い、ということではなく。
ミィ&仁義「なぁるほど。決して骨肉の争い、ということではなく。 エリィ「そういえば数回前に出そうと思っていた話を思い出したので出してみますね。言語によって読み方が違うという話の延長なのですが。」
エリィ「そういえば数回前に出そうと思っていた話を思い出したので出してみますね。言語によって読み方が違うという話の延長なのですが。」